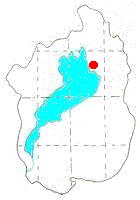1.はじめに
滋賀県には沢山の天井川があります。
滋賀県は周囲が山で囲まれており、滋賀県を水源とする120余りの川は、
わずかな例外を除いて、全て琵琶湖に流れ込んでいます。そのため、短距離
を山から流れ落ちる川が土砂を運んで河床が高くなり、天井川が作られまし
た。
天井川とは、「河川の運搬した砂礫が堤防の間を埋めて、河床が周囲の平
野面よりも一段と高くなったもの」(広辞苑)です。
今回ご紹介する川は、湖北にある田川(たがわ)です。
この川は、天井川からの逆流を避けるため、先人の必死の努力により、天井
川の下を潜って放水路に接続された珍しい川です(田川自体は天井川ではあ
りません)。
2.田川の場所
まず、場所を確認してみましょう。
湖北で最長の姉川は、伊吹山麓に始まって西に流れ、余呉湖の東に発して南
下する高時川と合流し、琵琶湖へ注いでいます。小谷山の周囲の水を集めて
流れる田川は、姉川と高時川の中間にあります。かつては三つの川が一箇所
で合流していました。

現在、この合流場所付近で、
田川は高時川と立体交差して
います。
1:田川
2:高時川
3:姉川
4:草野川
A:西野隧道
B:雨森芳洲庵
C:小谷城址
D:姉川古戦場跡
←広域地図
.jpg)
左図は三川の合流地点付近
の詳細地図です。
合流地点は、長浜駅の北方
約5キロの位置にあります。
R8(国道8号線=昔の北
国街道)を北上し、姉川大橋
を越えて間もなく左折すると、
田川と高時川の交差する場所
に着きます。
←合流点付近の地図*
本稿では、参考図書として、虎姫町教育委員会・編集(平成21年11月
発行)の「ふるさと虎姫 田川の歴史を知る」を参照させていただきました。
*印を付した写真等は、同資料から引用させていただいたものです。
なお、虎姫町は他の近隣5町(湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅
井町)と共に、今年(2010年)1月1日をもって長浜市に編入しました。
3.田川カルバート
現場を訪ねる前に、現場付近の様子を上空から眺めてみましょう。
思い切って大枚を投じ、ヘリコプターをチャーターして写真を撮りました!
この写真の中央辺りがJR虎姫駅を囲む虎姫町中心部、上部中央の山に浅井
長政が構えた小谷城址、中央を斜めに流れているのが本稿の主題である田川
です。(念のため、チャーター代は私が工面した...わけではありません)
.jpg) ↑上空から見た虎姫町*
↑上空から見た虎姫町*
まず、高時川と姉川が天井川であることを確認しておきましょう。
左下の写真は、田川が高時川の下を潜っている横にある錦織橋の上流側を
見たものです。高時川の堤防は、二階建て住居の二階に近い高さであること
が分かります。
後述するように、田川カルバート(地下水路)は、現在は錦織橋の下流側
にありますが、初期には上流側に設けられました。写真の水底に見える石の
造作は初期のものと思われます。
右下の写真は、国道8号線が通っている姉川大橋の付近で、向かって左端
にある姉川の堤防に、正面の国道8号線が上っていく場所です。姉川の堤防
は、8号線の向こうに建っている2階建ての住居の屋根に近い高さであるこ
とが分かります。
.jpg) ←高時川(錦織橋の上流側)
↓姉川の堤防
←高時川(錦織橋の上流側)
↓姉川の堤防
.jpg)
田川は、かつては錦織橋より少し下流で高時川に連なっていたそうです。
高時川と姉川の合流地点に近い場所なので、三川が合流していたと言えます。
そのため、天井川である高時川と姉川の水量が増すと、田川へ逆流し、田川
周辺はしばしば水害に遭っていたそうです。
では、水害を避けるために作られた田川カルバートを見てみましょう。
カルバート(culvert)とは、道路や堤防などの下を横切る俳水路の意味で、
日本語では「伏越樋(ふせこしひ)」と呼んでいたようです。ひらたく言え
ば「暗渠(あんきょ)」に相当すると思われます。なぜ外国語が当てられて
いるのかというと、明治時代に日本の土木指導にあたっていたオランダ人の
ヨハネス・デ・レーケの指導を仰いだためのようです。
.jpg) ←カルバートへの入り口
(正面が高時川の堤防)
↓錦織橋(向かって右が下流)
←カルバートへの入り口
(正面が高時川の堤防)
↓錦織橋(向かって右が下流)
.jpg)
.jpg) ←錦織橋に沿っているカルバート
(高時川下流側)
↓カルバートの出口
←錦織橋に沿っているカルバート
(高時川下流側)
↓カルバートの出口
.jpg)
.jpg) ←琵琶湖に向かう放水路
←琵琶湖に向かう放水路
高時川の下を潜ってきた水は
放水路で琵琶湖へ向かいます。
放水路は掘り下げられているた
め、流れはゆったりしています。
↓琵琶湖岸の放水路
.jpg)
姉川の様子も見てみましょう。
.jpg)
田川カルバートの少し先、300
メートル位下流、で高時川と姉川が
合流しています。
高時川は「妹川」とも呼ばれてき
たようです。
←合流地点
(右から姉川、左から高時川)
.jpg)
合流地点から下流の名称は姉川です。
琵琶湖湖岸の河口はゆったりしています。
←合流地点から見た下流
↓琵琶湖に注ぐ姉川河口
.jpg)
ついでに姉川の上流を一箇所眺めてみます。
姉川と聞けば、かつての合戦場を思い起こす人が多いかと思います。
400年以上前の合戦当時は、戦闘が繰り広げられた辺りには堤防がなかっ
たか、あっても貧弱だったに違いなく、姉川の氾濫は手に負えなかったので
はないかと思われます。
.jpg) ←姉川古戦場
↓古戦場付近の姉川(後方に伊吹山)
←姉川古戦場
↓古戦場付近の姉川(後方に伊吹山)
.jpg)
さて、もう一度田川に戻ります。
先に掲げた航空写真を見ると、田川は比較的直線的ですっきり伸びています。
.jpg)
これは直流化工事によるもので
すが、昔は随分と蛇行して深い淵
が沢山ありました。
そのため、虎姫のむかし話には、
河童や大蛇などが田川に住んでい
た、などの言い伝えが残されてい
ます。
←田川新旧比較図(大正4年)*
初期の田川カルバートが完成したのは明治18年です。
しかし、その後もしばしば水害が発生したため、改良が積み重ねられました。
カルバートの寸法の変化(田川治水事業年賦*から抜粋)
■明治18年(1885)カルバート竣工:
高さ2.0m、幅3.0m、長さ109m、 流量 49立米/秒・2連
■昭和 4年(1929)拡幅工事:
高さ2.3m、幅3.6m、長さ98.3m、流量 49立米/秒・2連
■昭和41年(1966)新カルバート竣工:
高さ4.2m、幅4.2m、長さ216m、 流量109立米/秒・2連
このように、田川はカルバートによって高時川から遮断されているため、
現在では水害がなくなっているようです。
4.江戸時代の田川治水事業
ここで、田川治水事業の歴史を追ってみると、概略次のとおりです。
| 安政 元年 | 1854 | 高時川との合流点を約50メートル下流に付け替え |
| 万延 元年 | 1860 | 木製伏越樋竣工 総事業費8万両 |
| 万延 2年 | 1861 | 田川逆水門竣工 |
| 明治18年 | 1885 | 洋風レンガ造りの田川カルバート竣工 総事業費7万円 |
| 明治21年 | 1888 | 田川改良逆水門および井堰竣工 |
| 明治27年 | 1894 | カルバート修繕工事竣工 |
| 大正 3年 | 1914 | 田川直流工事竣工 |
| 昭和 4年 | 1929 | 鉄筋コンクリート造のカルバートを継ぎ足す工事竣工
総事業費約3万9千円 |
| 昭和41年 | 1966 | 田川中小河川改良工事による新カルバート竣工
総事業費約1億1千7百万円 |
(田川治水事業年賦*から抜粋)
この年表を見ると、驚くべき事実に気づきます。それは、田川カルバート
が築かれた明治時代よりも前の江戸時代に、既に同様の工事が行われていた
という事実です。
田川カルバートは、カルバートという横文字が当てられていることからし
て、明治時代に外国人の設計で施工された新しい技術かと思いました。しか
し、明治18年よりも四半世紀も前の江戸時代に、日本人の手によって木製
の伏越樋(=カルバート)が築かれていたのでした。
流砂量の多い姉川と高時川は天井川化が進み、長雨や大雨の度に河床の低
い田川へ水が逆流し、上流の唐国村、月ヶ瀬村、田村、酢村は洪水や浸水に
襲われていたようです。越前に向かう北国街道(現・国道8号線)も水没し
て、舟や筏を使う有様だったそうです。
.jpg)
この四カ村の田川治水に関する
歴史が「四カ字共有文書」として
残っています。
←四カ字共有文書*
古文書に記録されている治水事業とその経緯の詳細は割愛します。
要するに、幕府(大津代官)の許可の下に、木製の樋を高時川の下に敷設し
て田川の水を通過させる水路が万延元年(1860年)に完成したそうです。
ちなみに、四カ村のひとつの田村は、安政5年(1858年)に大老とな
り、安政7年(1860年)に暗殺された井伊直弼(井伊掃部頭)の領地で
した。(安政7年は3月18日から万延に改元)
ところで、虎姫四カ村は新川開削の許可を願い出るにあたり、技術的な問
題を事前に検討していました。
美濃国大垣は豊富な地下水に恵まれていた一方、洪水常襲地域だったそう
です。揖斐川と牧田川の合流地点である大垣輪中の南部(現在の名神高速大
垣ICの南付近かと思います)は村より川底が高くなっていたため、伏越樋
を設置することによって輪中内にたまる悪水を排出させました。
「輪中(わじゅう)」とは、洪水から田畑や家屋を守るために、村の周り
を堤防で囲んだもの、だそうです。
.jpg)
伏越樋は天明5年(1785年)
に完成。その後30年毎に樋管が取
り替えられ、本格的な河川工事によ
り明治38年(1905年)に役目
を終えました。
←伏越樋のしくみ*
(大垣市輪中館資料より転載)
虎姫四カ村の代表は大垣を事前に視察した、ということです。
5.西野隧道
湖北の天井川訪問のついでに、「西野隧道」を訪ねてみましょう。
旧・高月町の琵琶湖に近い一画(本稿の最初に掲載した広域地図のA)に、
西野隧道があります。
.jpg)
ここ西野地区は西と北に低い山が
あり、東側に余呉川が流れています。
この川がしばしば氾濫したため、
放水路として山にトンネルを掘りま
した。石工がノミで岩盤を掘り、5
年かけて弘化2年(1845年)に
完成したそうです。
←西野地区
初代の西野隧道は全長220メートル。ノミの痕が残っており、一人がや
っと通れるだけの広さです。
昭和に入り、2代目の放水路(全長245メートル:現在は琵琶湖側への
連絡通路として使用)が昭和25(1950年)に作られ、現在の放水路で
ある3代目(全長252メートル)が昭和55年(1980年)に作られま
した。
.jpg) ←初代の西野隧道
現在の西野隧道(余呉川放水路)
↓写真右端付近から初代、2代、3代
←初代の西野隧道
現在の西野隧道(余呉川放水路)
↓写真右端付近から初代、2代、3代
.jpg) 6.おわりに:
6.おわりに:
田川カルバートの存在を知った時、これは外国人が持ち込んだ新しい技術
だろうと思いました。しかし、江戸時代に日本人の手によって同様の工事が
田川で既に行われていたことを知って驚きました。
さらに、田川カルバートよりも100年前に、美濃の国(岐阜県)で同様
の排水工事が実施されていた、ということは一層の驚きでした。
地下に俳水路を通す、という考え自体は単純で、歴史的に見たら新規性が
ないかも知れません。エジプトやローマでは随所に施工されていたのだろう
と思います。しかし、古代社会では、多分、権力者の指示に基づいて施工さ
れていただろうと思われるのに対し、田川の木製伏越樋は生活者の願望に基
づいて実現した、という点で賞賛されるべきだろうと思います。当時の8万
両という莫大な工事費は、受益者たる12カ村が彦根藩から借用して支払っ
たそうです。

「近江の散策」を立ち上げた当初、「妓王井川」
の記事を掲載しました。
妓王井川の流れに沿って歩いた時、流れが途
中で途絶えている場所がありま した。
そこは道路の下の暗渠を流れていたのでした。
その時は気づかなかったのですが、そこは天井
川だった家棟川があった場所でした。
←地下を潜り抜けてきた祇王井川
長浜市の北部に、伊吹山(1,377m)に次ぐ高さ(1,317m)の
金糞(かなくそ)山があります。かなくそとは、古代タタラ製鉄のカナグソ
(製鉄の屑)を意味しているようです。湖北では古くから製鉄が行われ、燃
料の木材を伐採したことが、高時川や姉川の天井川化を招いたひとつの要因
のようです。
本稿に登場する高時川と姉川は、現在も天井川として健在です。
本稿を「消えゆく」天井川シリーズに加えるのは相応しくないかも知れませ
んが、川のシリーズということで、水に流してくださいませ。
(散策:2010年4月28日)
(脱稿:2010年6月25日)
参考図書:
1.「ふるさと虎姫 田川の歴史を知る」 平成21年11月
執筆・編集:福井智英(学芸員) 発行:虎姫町教育委員会
2.「田川沿革誌」 平成7年年3月
編集・発行:滋賀県長浜土木事務所
3.「虎姫のむかし話」 昭和54年3月15日
編集:虎姫むかし話編集委員会 発行:虎姫町公民館
4.「虎姫のむかし話 第2集」 昭和55年3月31日
編集・発行:虎姫町教育委員会
ご参考:(本稿に関連する掲載済みの記事)
1.
消えゆく天井川
2.
消えゆく天井川(その2)
3.
祇王井川
------------------------------------------------------------------
現在、この合流場所付近で、 田川は高時川と立体交差して います。 1:田川 2:高時川 3:姉川 4:草野川 A:西野隧道 B:雨森芳洲庵 C:小谷城址 D:姉川古戦場跡 ←広域地図
左図は三川の合流地点付近 の詳細地図です。 合流地点は、長浜駅の北方 約5キロの位置にあります。 R8(国道8号線=昔の北 国街道)を北上し、姉川大橋 を越えて間もなく左折すると、 田川と高時川の交差する場所 に着きます。 ←合流点付近の地図* 本稿では、参考図書として、虎姫町教育委員会・編集(平成21年11月 発行)の「ふるさと虎姫 田川の歴史を知る」を参照させていただきました。 *印を付した写真等は、同資料から引用させていただいたものです。 なお、虎姫町は他の近隣5町(湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅 井町)と共に、今年(2010年)1月1日をもって長浜市に編入しました。 3.田川カルバート 現場を訪ねる前に、現場付近の様子を上空から眺めてみましょう。 思い切って大枚を投じ、ヘリコプターをチャーターして写真を撮りました! この写真の中央辺りがJR虎姫駅を囲む虎姫町中心部、上部中央の山に浅井 長政が構えた小谷城址、中央を斜めに流れているのが本稿の主題である田川 です。(念のため、チャーター代は私が工面した...わけではありません)
↑上空から見た虎姫町* まず、高時川と姉川が天井川であることを確認しておきましょう。 左下の写真は、田川が高時川の下を潜っている横にある錦織橋の上流側を 見たものです。高時川の堤防は、二階建て住居の二階に近い高さであること が分かります。 後述するように、田川カルバート(地下水路)は、現在は錦織橋の下流側 にありますが、初期には上流側に設けられました。写真の水底に見える石の 造作は初期のものと思われます。 右下の写真は、国道8号線が通っている姉川大橋の付近で、向かって左端 にある姉川の堤防に、正面の国道8号線が上っていく場所です。姉川の堤防 は、8号線の向こうに建っている2階建ての住居の屋根に近い高さであるこ とが分かります。
←高時川(錦織橋の上流側) ↓姉川の堤防
田川は、かつては錦織橋より少し下流で高時川に連なっていたそうです。 高時川と姉川の合流地点に近い場所なので、三川が合流していたと言えます。 そのため、天井川である高時川と姉川の水量が増すと、田川へ逆流し、田川 周辺はしばしば水害に遭っていたそうです。 では、水害を避けるために作られた田川カルバートを見てみましょう。 カルバート(culvert)とは、道路や堤防などの下を横切る俳水路の意味で、 日本語では「伏越樋(ふせこしひ)」と呼んでいたようです。ひらたく言え ば「暗渠(あんきょ)」に相当すると思われます。なぜ外国語が当てられて いるのかというと、明治時代に日本の土木指導にあたっていたオランダ人の ヨハネス・デ・レーケの指導を仰いだためのようです。
←カルバートへの入り口 (正面が高時川の堤防) ↓錦織橋(向かって右が下流)
.jpg)
←錦織橋に沿っているカルバート (高時川下流側) ↓カルバートの出口
.jpg)
←琵琶湖に向かう放水路 高時川の下を潜ってきた水は 放水路で琵琶湖へ向かいます。 放水路は掘り下げられているた め、流れはゆったりしています。 ↓琵琶湖岸の放水路
姉川の様子も見てみましょう。
田川カルバートの少し先、300 メートル位下流、で高時川と姉川が 合流しています。 高時川は「妹川」とも呼ばれてき たようです。 ←合流地点 (右から姉川、左から高時川)
合流地点から下流の名称は姉川です。 琵琶湖湖岸の河口はゆったりしています。 ←合流地点から見た下流 ↓琵琶湖に注ぐ姉川河口
ついでに姉川の上流を一箇所眺めてみます。 姉川と聞けば、かつての合戦場を思い起こす人が多いかと思います。 400年以上前の合戦当時は、戦闘が繰り広げられた辺りには堤防がなかっ たか、あっても貧弱だったに違いなく、姉川の氾濫は手に負えなかったので はないかと思われます。
←姉川古戦場 ↓古戦場付近の姉川(後方に伊吹山)
さて、もう一度田川に戻ります。 先に掲げた航空写真を見ると、田川は比較的直線的ですっきり伸びています。
これは直流化工事によるもので すが、昔は随分と蛇行して深い淵 が沢山ありました。 そのため、虎姫のむかし話には、 河童や大蛇などが田川に住んでい た、などの言い伝えが残されてい ます。 ←田川新旧比較図(大正4年)* 初期の田川カルバートが完成したのは明治18年です。 しかし、その後もしばしば水害が発生したため、改良が積み重ねられました。 カルバートの寸法の変化(田川治水事業年賦*から抜粋) ■明治18年(1885)カルバート竣工: 高さ2.0m、幅3.0m、長さ109m、 流量 49立米/秒・2連 ■昭和 4年(1929)拡幅工事: 高さ2.3m、幅3.6m、長さ98.3m、流量 49立米/秒・2連 ■昭和41年(1966)新カルバート竣工: 高さ4.2m、幅4.2m、長さ216m、 流量109立米/秒・2連 このように、田川はカルバートによって高時川から遮断されているため、 現在では水害がなくなっているようです。 4.江戸時代の田川治水事業 ここで、田川治水事業の歴史を追ってみると、概略次のとおりです。
この四カ村の田川治水に関する 歴史が「四カ字共有文書」として 残っています。 ←四カ字共有文書* 古文書に記録されている治水事業とその経緯の詳細は割愛します。 要するに、幕府(大津代官)の許可の下に、木製の樋を高時川の下に敷設し て田川の水を通過させる水路が万延元年(1860年)に完成したそうです。 ちなみに、四カ村のひとつの田村は、安政5年(1858年)に大老とな り、安政7年(1860年)に暗殺された井伊直弼(井伊掃部頭)の領地で した。(安政7年は3月18日から万延に改元) ところで、虎姫四カ村は新川開削の許可を願い出るにあたり、技術的な問 題を事前に検討していました。 美濃国大垣は豊富な地下水に恵まれていた一方、洪水常襲地域だったそう です。揖斐川と牧田川の合流地点である大垣輪中の南部(現在の名神高速大 垣ICの南付近かと思います)は村より川底が高くなっていたため、伏越樋 を設置することによって輪中内にたまる悪水を排出させました。 「輪中(わじゅう)」とは、洪水から田畑や家屋を守るために、村の周り を堤防で囲んだもの、だそうです。
伏越樋は天明5年(1785年) に完成。その後30年毎に樋管が取 り替えられ、本格的な河川工事によ り明治38年(1905年)に役目 を終えました。 ←伏越樋のしくみ* (大垣市輪中館資料より転載) 虎姫四カ村の代表は大垣を事前に視察した、ということです。 5.西野隧道 湖北の天井川訪問のついでに、「西野隧道」を訪ねてみましょう。 旧・高月町の琵琶湖に近い一画(本稿の最初に掲載した広域地図のA)に、 西野隧道があります。
ここ西野地区は西と北に低い山が あり、東側に余呉川が流れています。 この川がしばしば氾濫したため、 放水路として山にトンネルを掘りま した。石工がノミで岩盤を掘り、5 年かけて弘化2年(1845年)に 完成したそうです。 ←西野地区 初代の西野隧道は全長220メートル。ノミの痕が残っており、一人がや っと通れるだけの広さです。 昭和に入り、2代目の放水路(全長245メートル:現在は琵琶湖側への 連絡通路として使用)が昭和25(1950年)に作られ、現在の放水路で ある3代目(全長252メートル)が昭和55年(1980年)に作られま した。
←初代の西野隧道 現在の西野隧道(余呉川放水路) ↓写真右端付近から初代、2代、3代
6.おわりに: 田川カルバートの存在を知った時、これは外国人が持ち込んだ新しい技術 だろうと思いました。しかし、江戸時代に日本人の手によって同様の工事が 田川で既に行われていたことを知って驚きました。 さらに、田川カルバートよりも100年前に、美濃の国(岐阜県)で同様 の排水工事が実施されていた、ということは一層の驚きでした。 地下に俳水路を通す、という考え自体は単純で、歴史的に見たら新規性が ないかも知れません。エジプトやローマでは随所に施工されていたのだろう と思います。しかし、古代社会では、多分、権力者の指示に基づいて施工さ れていただろうと思われるのに対し、田川の木製伏越樋は生活者の願望に基 づいて実現した、という点で賞賛されるべきだろうと思います。当時の8万 両という莫大な工事費は、受益者たる12カ村が彦根藩から借用して支払っ たそうです。
「近江の散策」を立ち上げた当初、「妓王井川」 の記事を掲載しました。 妓王井川の流れに沿って歩いた時、流れが途 中で途絶えている場所がありま した。 そこは道路の下の暗渠を流れていたのでした。 その時は気づかなかったのですが、そこは天井 川だった家棟川があった場所でした。 ←地下を潜り抜けてきた祇王井川 長浜市の北部に、伊吹山(1,377m)に次ぐ高さ(1,317m)の 金糞(かなくそ)山があります。かなくそとは、古代タタラ製鉄のカナグソ (製鉄の屑)を意味しているようです。湖北では古くから製鉄が行われ、燃 料の木材を伐採したことが、高時川や姉川の天井川化を招いたひとつの要因 のようです。 本稿に登場する高時川と姉川は、現在も天井川として健在です。 本稿を「消えゆく」天井川シリーズに加えるのは相応しくないかも知れませ んが、川のシリーズということで、水に流してくださいませ。 (散策:2010年4月28日) (脱稿:2010年6月25日) 参考図書: 1.「ふるさと虎姫 田川の歴史を知る」 平成21年11月 執筆・編集:福井智英(学芸員) 発行:虎姫町教育委員会 2.「田川沿革誌」 平成7年年3月 編集・発行:滋賀県長浜土木事務所 3.「虎姫のむかし話」 昭和54年3月15日 編集:虎姫むかし話編集委員会 発行:虎姫町公民館 4.「虎姫のむかし話 第2集」 昭和55年3月31日 編集・発行:虎姫町教育委員会 ご参考:(本稿に関連する掲載済みの記事) 1.消えゆく天井川 2.消えゆく天井川(その2) 3.祇王井川